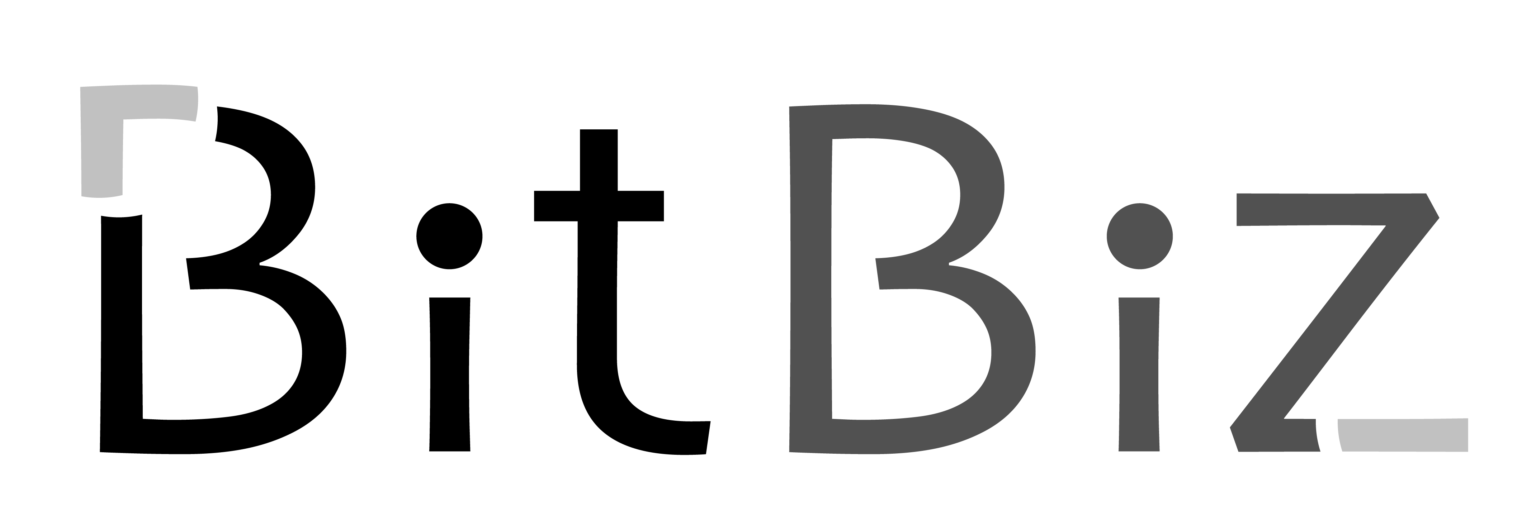ミドルステージにまで成長したベンチャー企業は、資金調達が進めやすくなるなどの変化(ミドルステージにおける資金調達についてはこちら)が起こるとともに、事業が本格的に進むことから内部の状況も大きく変化します。
その変化のうちの1つが従業員数の増加です。
そこでここでは、雇用機会が増したミドルステージにある企業が理解しておくべき基本的な法律上のルールについて解説していきます。
目次
ミドルステージにあるベンチャー企業と雇い入れについて
ミドルステージにおいては、雇用による人材確保を進めることになり、数十人以上の規模になることが考えられます。
そうすると、就業規則の整備をしなければならなくなりますし、雇用契約の締結にあたっては実務上、契約書の作成や労働条件通知書等の交付なども行うことになるでしょう。
また、比較的これまでの成長ステージ(シードステージやアーリーステージ)に比べると企業活動も安定してきますが、設備投資など大きな支出も伴うことから雇用にも慎重にならなくてはなりません。
そこで1つ考えられるのは契約期間の満了により雇用契約が解除できる契約社員としての採用です。
近年は「同一労働同一賃金」の考え方に基づき法改正もなされており、契約社員だからといって退職金を支給しないなどの差を設けることは認められませんが、労務管理上生ずる一定のリスクは抑えることができます。
ただ、従業員の雇用に関しては企業側が法律の知識を持って対応しなければなりません。
労働契約の締結
労働契約はそもそも口頭で締結することもできます。書面を用いなくても、双方が約しさえすれば適法に成立します。
ただ、書面などの証拠を残していなければ後々トラブルに発展する可能性があることから、一般的には記録として残るようにすべきと考えられています。
特にトラブルの素となりやすいのは労働条件に関することです。
労働条件に関して労働基準法は、同法で定める最低基準を下回ってはいけない旨規定しています。
実際、法律の定めを下回る条件に関しては無効になり、その場合には法律で定められた労働条件が適用されます。
この点留意して、労働条件を検討し、労働契約を締結させなくてはなりません。
なお、契約書内の表記が「委託」や「請負」とされていても、労働基準法が適用される可能性はありますので注意しましょう。
同法の適用を受けないように別の契約類型を採ったとしても、実態が使用者と労働者の関係と見られる場合には意味をなしません。
例えば以下の事柄に当てはまる場合には雇用関係にあると判断されやすいです。
- 業務上の指揮監督をしている
- 報酬に労務対償性がある
- 相手方に事業者性がない
- 相手方が自社に専属的である
有期労働契約のルール
冒頭で、ミドルステージにあるベンチャー企業が従業員を増やす手法として、契約社員の活用も例に挙げました。
そこで、有期労働契約に関するルールを整理しておきましょう。
最も基本的なことですが、有期労働契約は企業と従業員双方を拘束することになります。
つまり、特別の定めがなければ、原則として一方的な理由で解約をできません。
さらに、この「期間の定めのある契約」については原則3年を超えてはならないとも定められています。
3年ルールの例外
上の通り、期間に関しては原則3年を超えることはできないのですが、以下の場合には「5年以内」までなら伸ばすことが可能です。
- 公認会計士や医師、博士号取得者など高度で専門的な知識を有する者が、その知識を必要とする業務に就く場合
- 満60歳以上で、定年に達した後も引き続いて雇用する場合
また、土木工事など有期事業で必要な期間を定めている場合、労基法70条に基づき長期の職業訓練を要する場合などには、3年を超える契約が認められています。
労働条件通知書と雇用契約書の必要性
雇用にあたって契約書の作成は必須ではありませんが、紛争を防ぐためにも作成をしておくべきです。
これに対して「労働条件通知書」(雇入れ通知書)は、労働基準法および労働準法施行規則にて交付が義務付けられています。
この点混同しないよう注意しましょう。
正社員や契約社員、パート、アルバイトなどを問わず交付しなければなりません。
就業規則に関する法律

従業員を雇うなら就業規則を定めなくてはなりません。
これは職場でのルールなどを詳細に規定したもので、企業と従業員のルールブックとして機能します。
就業規則の作成が義務付けられるケース
就業規則は、「常時10人以上の従業員を雇用」する場合に作成が義務付けられています。
そして、作成後は管轄の労働基準監督署に届出も必要です。
なお、作成義務の有無に関しては以下の点に注意して判断しましょう。
- 10人以上とは出勤している人数ではなく、所属しているかどうか
- 全社的には10人以上が所属していても、事業場単位で見て10人以下なら義務はない
- 契約社員やパート、アルバイトも含む
- 1日数時間程度の勤務でも人数にカウントする
- 共通する内容の就業規則を適用していても、複数の事業場がある場合、原則それぞれで届出が必要(一定要件を満たし、本社で一括して届出することも可能)
就業規則はいつでも閲覧できる状態にする
就業規則は作成後、事業場へ備え付け、いつでも従業員が閲覧できる状態にしておかなければなりません。そこで、職場の見やすい場所へ提示したり、就業規則を配布したりといった対応を取ると良いでしょう。
また、社内LAN、イントラネットによる提示でも良いです。
逆に、社長や人事担当者の引き出しに収納されていたり、閲覧の際労務管理担当者に申し込む必要があったりしたのでは適法な運用とは言えません。
就業規則のうち、賃金規定だけを閲覧させないといった対応も認められません。
36協定の作成
残業や休日出勤が生じる場合、「36協定」を締結し、これも管轄の労働基準監督署へ届出をしなければなりません。
就業規則同様、本店だけでなく、事業場単位で必要です。
なお、36協定の対象期間は1年間に限られ、残業などを行わせる必要のある具体的事由を定めなければなりません。業務の範囲も明確化、締結時における労働者数、法定労働時間数を超える上限時間数なども定めます。
なお、今では電子申請も可能になっており、電子政府の総合窓口「e-Gov」(イーガブ)から申請ができるため手続上の負担は軽減されています。