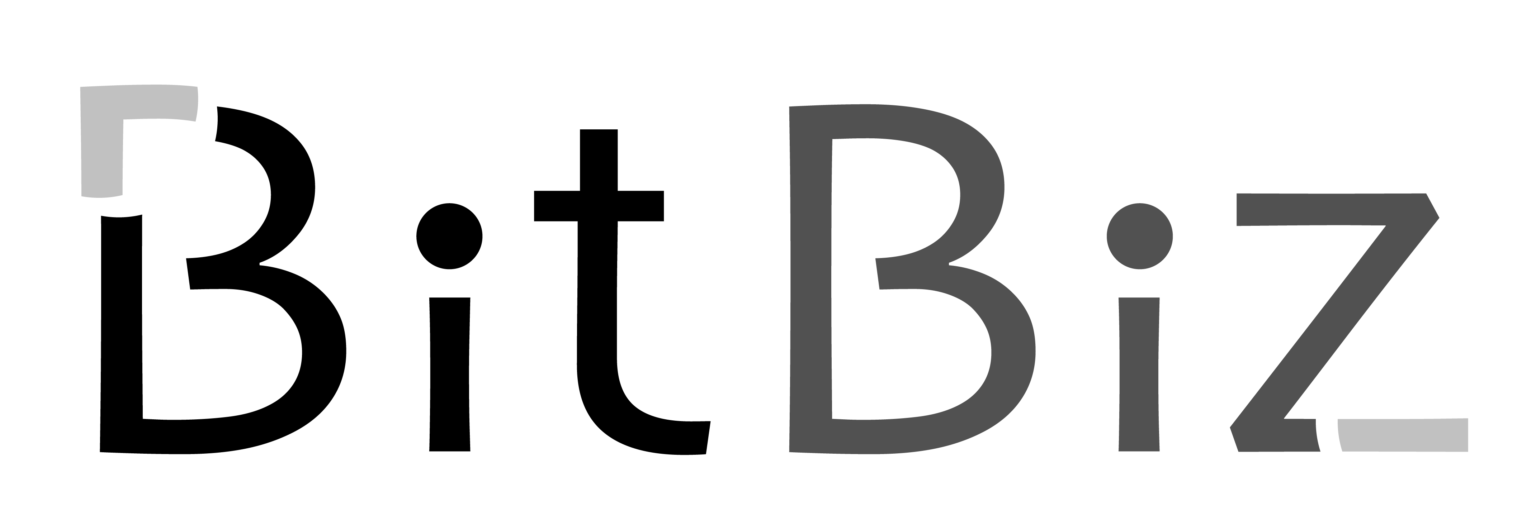シードステージでの特許対策(こちらのページで解説)だけで終わっては意味がありません。
そこでシードステージ行った特許出願に続き、アーリーステージでは以下の対策を進めていきます。
また、ここで解説する特許の知識を持って適切に対策を行うことで得られるメリットについても当記事で紹介しています。
目次
アーリーステージで2件目の特許出願
特許出願を一件行っただけで、その後の知的財産への取り組みが行われていないケースがあります。
実際、シードステージやアーリーステージにおいては別に注力すべき大きな問題があるため、特許に重きを置くことが難しいかもしれません。
しかし、最初の出願をしてからの1年間は、特許戦略で非常に重要です。
特許法では技術的な方向性の調整や改善なども考慮し、「先の出願の日から1年以内」に限り優先権を認めていることに由来します(特許法41条)。
この規定があることで、最初の出願後1年の出来事を反映させ、事業を保護するための特許出願ができるのです。
この際に行うべきこととしては以下の事柄が挙げられます。
先の出願内容の軌道修正
通常、特許の出願後、補正をしたくても簡単にはできません。
しかし、上述の通り、先の出願から1年以内であれば優先権の主張により対応が可能です。先の出願は取り下げられたものとみなされますが、1件目の内容は2件目の出願時に出願したものとみなされるため問題はありません。この仕組みを使い、とりあえず出願していた内容をバージョンアップさせることができます。
ただし、補正の内容は慎重に検討しなければなりません。
見るべきポイントの1つは、自社サービス等に改善や変更が生じた際、最初の特許出願で保護されるのかどうかという点です。
特にベンチャー企業の場合、急速に成長をしていくため、サービス等の内容も改善・変化が生じ得ます。
そこで急成長していくサービス等に適合する形で特許もなされなければなりません。出願内容を修正しなければいずれ保護されないおそれがあると評価できる場合には言葉を補うなどして2件目の出願で対応します。
他社や先行技術の調査
競合他社が出てきた場合、その企業の製品やサービスの動向を追っていくことが大切です。常に特許戦略で対応する必要はありませんが、対立関係が拮抗しているような場合には特許出願による強い牽制効果が期待できます。
そのためにも、先の特許出願で競合他社による製品・サービスを捉えられているか、といった分析が必要です。
また、先行技術文献について広く調査を実施することも大切です。
競合他社以外に、自社と近い技術が出願時に知られていなかったかどうかを確認するのです。自社で認識できる範囲には限界があるため、専門家、専門の調査会社などに依頼するのも良いでしょう。
アライアンス契約を意識した出願
続いての出願においては、アライアンス契約も視野に入れることが大事です。
アライアンス契約を平たく言うと、他社と共同で事業を実施することです。
シードステージやアーリーステージにあるベンチャー企業が自社だけの力でできることには限りがありますので、他社とのアライアンスが重要になってくるのです。大きな成長をする前段階から大きな競争力を得るための一つの戦略となります。
ただ、提携する他社と特許に関して問題が生じることがあるため、業務提携の可能性がある他社の製品やサービスに関しては特許の調査を行っておくことが望ましいです。
アライアンスを意識した上で、特許出願の内容に補正すべき箇所はないか、不足はないかといったところを評価していきます。
アーリーステージで特許戦略を進めるメリット

特許出願を戦略的に取り組むことで、以下のようなメリットが得られます。
競合他社にリスクを与えられる
シードステージおよびアーリーステージにて特許出願を行うことは、他社の追従・模倣などから守る機能を発揮し、同時にリスクを与えるという攻めの機能も発揮します。
ただ、特許の出願のみでは事実上の効果に留まります。特許権を行使してサービス等の差止の請求をしたり損害賠償の請求をしたりするには、特許が認められていなければなりません。
特許出願の審査は審査請求を待って行うこととされているため、いつ審査請求を行うのか、タイミングに関しても他社との関係やコストなどを考慮して戦略的に決定することが大切です。
交渉の材料として使える
業務提携の契約をする際、契約内容にライセンスが入ることも考えられますので、特許は交渉の材料としても使えます。
また、その後の成長ステージにて投資を受けるときやM&A、IPOにおける企業価値の評価を受けるときも良い判断材料となります。
DDにおけるリスク評価で悪くならない
アーリーステージで特許出願を済ませて特許を成立させておけば、その後のステージにおいてDD(デューデリジェンス)を受けたときも評価を落としにくいです。逆にDDを受ける段階に至ってから他社特許の調査などをしたのでは知財リスクが大きく、エグジットに際しての障害となってしまうおそれがあります。